みなさんこんにちは!
最近は暑い日が増えてきて夏が近づいている感じがしますね。
これからの季節は高温多湿になるため、細菌が増加し、食中毒が起こりやすい時期となります。
食中毒は飲食店だけでなく、家庭でも起こりやすいのでしっかりと予防をすることが大切です。

食中毒とは?
食中毒とは細菌やウイルスが付着した食べ物を食べることによって
下痢や嘔吐、腹痛、発熱などの症状が出る事です。
原因となる細菌の代表的なものは、腸管出血性大腸菌(O157、O111など)や
カンピロバクター、サルモネラ属菌などがあり、食中毒を引き起こす細菌のほとんどは、
室温(約20℃)で活発に増殖し始め、人間や動物の体温ぐらいの温度で増殖のスピードが最も速くなります。
家庭で発生した場合は症状が軽かったり、発症する人が1人や2人のことが多いことから
風邪や寝冷えなどと思われがちで、食中毒とは気づかれず重症になることもあるので注意が必要です。

食中毒予防の3原則
食中毒予防の3原則とは、
①菌をつけない
②菌を増やさない
③菌をやっつける です。
この3つのそれぞれのポイントについてお話します。
①菌をつけない
菌をつけないためには食べ物を触る人の手や調理器具を清潔に保つことと、
食材に付着している菌を他の食材や器具に移さないことが重要です。
肉や魚の水分などが他の食材につかないようにしたり、冷蔵庫で保管する
場合は他の食材に触れない様にしましょう。
また、調理中は使う食品ごとに手や調理器具を洗うといいでしょう。
特に肉や魚、卵などを使った場合は念入りに洗ってください。
手や調理器具、食器などを拭く物は常に清潔なものを使用してくださいね。
調理済みの食品を保管する際は、密閉できる容器に入れて保管してください。
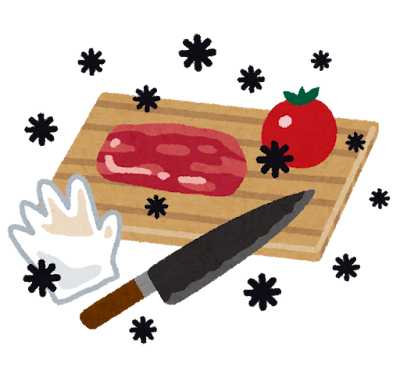
②菌を増やさない
冷蔵庫内の温度を一定に保つこと、食材を常温で放置しないことが重要です。
細菌は10℃以下では増殖がゆっくりとなり、マイナス15℃以下では増殖が停止します。
食べ物に付着した菌を増やさないためには、低温で保存することが大切です。
冷蔵庫内を10℃以下、冷凍庫をマイナス15℃以下に保つために、物を詰め込み過ぎないようにしましょう。
全体の7~8割くらいが目安です!
また、買い物の際には冷蔵、冷凍食品は買い物の最後にカゴに入れるようにしてできるだけ低い温度を保てるようにするのがおすすめです。
ですが、低い温度を保っても細菌はゆっくりと増殖していくので食べ物は早めに食べるのが1番です!
③菌をやっつける
ほとんどの細菌やウイルスは加熱によって死滅するので、肉や魚はもちろん、野菜なども加熱して食べれば安全です。
特に肉料理は中心までよく加熱することが大事です。目安は中心温度を75℃で1分以上です。
また、残った食品などを再度食べる場合もしっかりと再加熱して食べることが大切です。
そして、調理で使った包丁などの器具は洗剤でしっかりと洗ってください。
包丁の持ち手やまな板の裏面、側面なども忘れない様に洗ってくださいね。
最後に煮沸消毒や漂白剤を用いることでさらに効果的に殺菌消毒できます。
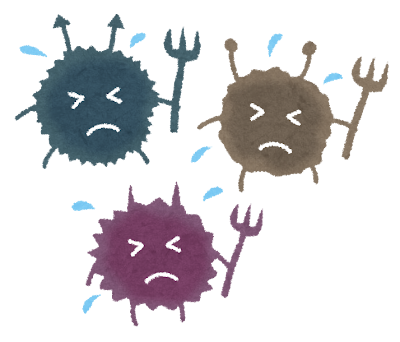
免疫力も大事!
食中毒は食中毒予防の3原則を守ることで予防することができますが、
やはり自分自身の免疫力が大きく関わってきます。
同じものを食べても食中毒を発症する人としない人に分かれるのは免疫力の違いです。
4月から新しい職場や学校になり、生活習慣が今までと変わったという方が多いと思いますが、6月は4月から溜まった疲れが出やすい時期です。
疲れやストレスを溜め込まず、休日には趣味を満喫したり、しっかりと体を休めたりしてリフレッシュしてくださいね!
また生活習慣の乱れも免疫力低下の1つの原因です。
規則正しい生活をし、しっかり栄養と睡眠をとって免疫力を維持しましょう!



